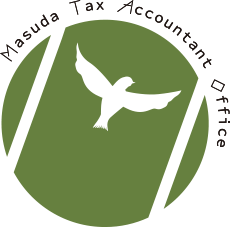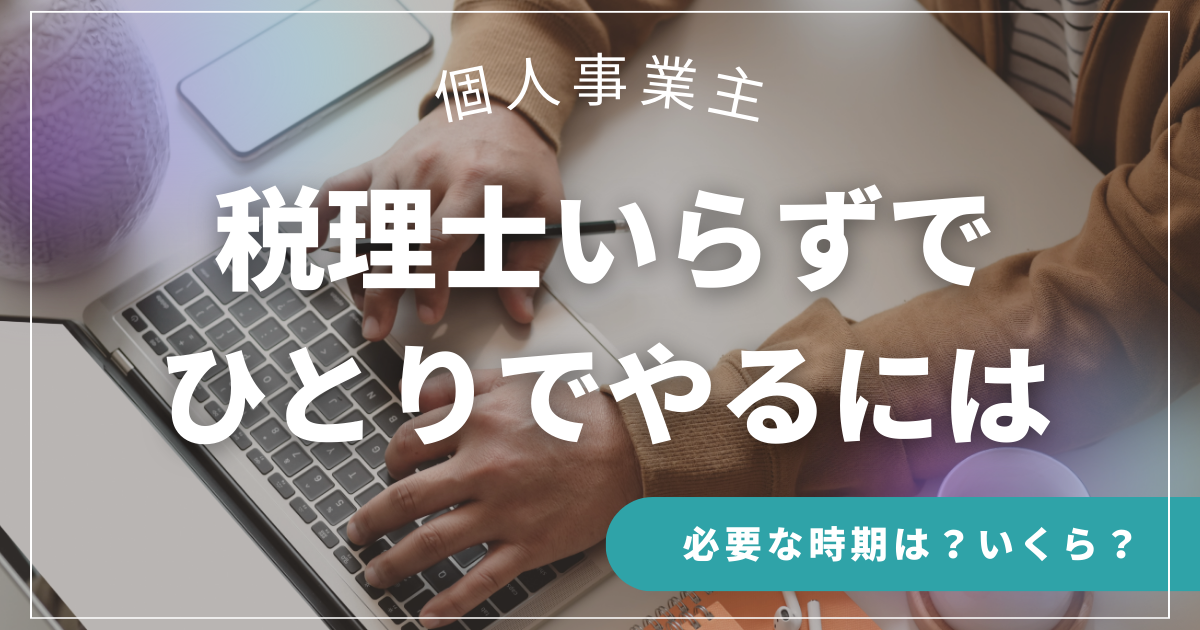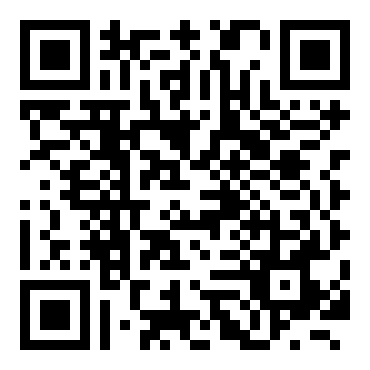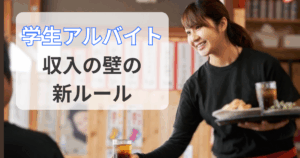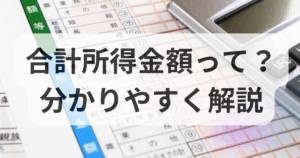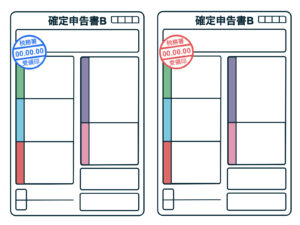個人事業主さんって「税理士」は必要ない!?
みなさんの中には、
 お客様の声
お客様の声いつから依頼するのがいいですか?



いくら位かかるものなんでしょうか??
などと、疑問に思うことはありませんか?
税理士を必要としない理由や、そのメリット・デメリットについて解説します。
まずは「税理士ってどんな事してくれるの?」からお話しますね。
税理士へ依頼できること
個人事業主さんにとって一般的な「税理士を必要とする場面」を考えてみましょう。と、その前に
税理士は、税務申告や会計処理を専門的に行うプロフェッショナルです。
例えば、
「私は青色申告の方が良いですか?」
「私の確定申告書作成してください」
などは、「税理士」以外回答できませんので
ニセ税理士にはご注意ください。
税務申告書(確定申告書)の作成・提出
メインとしては、
・所得税の確定申告書
・消費税(インボイス)の確定申告書
の作成と提出、でしょうか。
また、確定申告書をつくるためには
個人事業の収支をまとめる必要があります。
そのために領収書などを整理して
会計ソフトに入力したり
入力された会計ソフトをチェックして
追加の入力をして、決算書の作成をしていきます。



入力や確定申告書を作成するときは、お客様の事業と未来を想像しながら作って行きます。領収書から行動が見れますし「この時期お忙しそうだったなぁ」など思い出しています。
税金関連の書類の作成・提出/ 年末調整
インボイスの登録をするとなれば、その申請書類の作成・提出、
スタッフを雇っていれば、給与計算や年末調整のフォロー、
源泉所得税や住民税を天引きしていれば、その管理などです。
「支払ってくださいね~」と連絡します。
税金・経営の相談
個人事業としてやっていて経営で不安になったり、
わからないことがあれば相談できます。
税金のスケジュール管理などもそうですし、
融資の判断・書類のフォロー、
補助金、助成金の申請のお手伝い
インボイスの登録をしたらいいのかの質問では、その時期など助言いたします。
税務署・税務調査の対応
個人事業主さん、実際に税務調査は多くありませんが、
ゼロではありません。
税務調査ではないけど「行政指導」で
税務署からお尋ね(お手紙)が届いたり、
電話での確認などがあったとき税理士が窓口になります。


他の士業との連携・紹介
税理士の裏には、沢山の業者さん、会社さんなど知り合いが多いので
どなたか紹介できるケースがあります。
「弁護士さん紹介してください」など聞いていただくことが可能です。
税理士を依頼しない場合のリスク
以上から、税理士を依頼しない場合、以下のようなリスクが考えられます。
・税務申告のミスによるペナルティ
・経費の計上漏れ・二重計上の防止
・税務調査に対する不安
これらのリスクは、特に税務知識が不足している場合に顕著です。
自分で処理する場合は、正確な知識を持つことが重要です。
税理士を依頼しないメリット
では逆に、税理士を依頼しないことのメリットについて考えてみましょう。
コストが削減できる
税理士に依頼する場合、料金が発生します。
個人事業主さんでも規模感は様々ですが、
資金が潤沢にないケースが多いので
税理士への料金を削減することで、
他の部分に資金がかけられるようになります。
具体的には、以下の方法でコスト削減が可能です。
これにより、支出を抑え、事業の成長に資金を回すことができます。
自由度の高い経営が可能になる
税理士から質問に回答する手間を省けます。
自分のペースで業務を進められるため「楽」という方もいるでしょう。
自分でできる確定申告の方法
確定申告は、個人事業主にとって重要な業務です。
しかしながら、自分でも行うことができます。
その時は以下のステップで進めることが可能です。
- 収入と経費を整理する
- 必要な書類を準備する
- 決算書&確定申告書を作成する
- 提出する
- 納税する
これらのステップを踏むことで、税理士に依頼せずともスムーズに申告を行うことができます。
自力で頑張ることで、強制的に学ぶ状況をつくることができますね。
税理士不要でもできる会計処理
税理士がいなくても、特に「会計処理」は自力で行うことが可能です。
「会計処理」というのは、
個人事業での収支を集計していくことです。
最近では便利な会計ソフトが多く登場しており、
個人事業主でも簡単に利用できます。
以下に、自力での会計処理のポイントを紹介します。
手書きで記帳のポイント
自力で手書きの記帳を行う際は、特に正確性が重要です。
計算ミスには注意しましょう。
また取引の多さによりますが
・毎日記帳を行う
・領収書を整理する
・定期的に収支を確認する
これにより、確定申告書の作成の負担を軽減できます。


おすすめの会計ソフトとその活用法
会計ソフトを利用することで、記帳や申告が格段に楽になります。
以下は、おすすめの会計ソフトです。
これらのソフトを活用することで、効率的に会計処理を行うことができます。
税務書類作成のコツ
確定申告書や、税務署へ提出する申請書類を自分で作成する際は
以下のコツを押さえておくと良いでしょう。
これにより、スムーズに書類を作成し、提出することが可能です。
税理士への依頼が必要なケース
税理士として仕事をする中で、依頼された方がいい、と思うケースも存在します。
特に、事業が成長するにつれて、税務処理が複雑になることがあります。
以下に、依頼が必要なケースを紹介します。
税務調査の連絡があったとき
税務調査の連絡が入ったら、ご自身で対応されることもできますが、
税理士に依頼するのがいいと考えます。
税理士が依頼を受けましたら、
・帳簿を整備する
・必要な書類を揃える
・事前にリハーサルなど
を行い、税務調査に対する不安を軽減できます。
インボイス(消費税)の登録をするとき
インボイスの登録をしようとするときは、消費税の確定申告・納税が必要になります。
消費税というのは、理解しづらくて、更には会計処理も特殊になることがあるので
一度見てもらうのがいいです。



知らないでいると、本当なら還付を受けられるのに納税になった、なんてことがあるので。
複雑な確定申告が必要なとき
確定申告が複雑な場合、税理士に依頼することが有効です。
特に、以下のような場合は注意が必要です。
・不動産を売ったとき
・法人成りをしたその年(引継ぎのための処理)
・インボイスの登録をしたとき
・複数の収入源があるとき
・開業したときで減価償却資産が高額で複数あるとき
このような場合、専門的な知識を持つ税理士に依頼することで、
正確な判断が可能になります。
会社をつくることを考えているとき
そろそろ法人化を、、、!
そんな時にも相談をされるのもいいです。
・会社経営を考えつつの決算月をいつにするか
・個人事業との引継ぎで税金発生を最小限に抑える
・司法書士さん等への引継ぎ
このような時は、事前に1度でも相談されると良いです。
税理士不要を選択する前に考えるべきこと
税理士不要を選択する前に、いくつかのポイントを考慮することが重要です。
特に、税務に関する基礎知識や時間のコストを考える必要があります。
個人事業主が知っておくべき基礎知識
税務に関する基礎知識を持つことは、個人事業主にとって非常に重要です。
ただ、依頼しない場合、時間や労力がかかることがあります。
自分で処理する場合、以下の点を考慮しましょう。
・どれくらいの時間がかかるか
・自分のスキルで対応できるか
これにより、税理士を依頼するかどうかの判断がしやすくなります。
税務に関する知識の収集
税務に関する不安がある場合、
最寄りの税務署で相談してすすめることも可能です。
また書籍やYouTubeで、いろいろな情報がでていますから
これらを活用しご自身で経営能力をあげていけます。
当事務所では公式LINEで情報を配信しています。
定期的に個人事業主・フリーランスさんへ、税務情報を無料でお送りしています。
税理士を活用する場合
自分でやることを考えるつつ、
税理士を活用することで得られるメリットも多くあります。
特に、経営の安定性や専門的なアドバイスが得られる点が挙げられます。
依頼する方法(形態)についてと、時期についてです。
月額で顧問料を払う
税理士を専属的に顧問として依頼することで、
経営に関するアドバイスを受けることができます。
これにより、税務だけでなく、経営全般においてもサポートを受けることが可能です。
特に、事業が成長する際には、専門的な知識が役立ちます。
ただし、依頼する税理士によって料金形態が異なります。
・領収書整理などの記帳部分の月額か
・税務や経営の相談が含まれるのか
こちらは事前に確認しましょう。
単発でアドバイスを受ける
税理士から随時アドバイスを受けるスポット相談では
会計処理の疑問や、
今度どうして行こうか、など
必要な時に必要な分だけ受けるスポット(単発)相談というのがあります。
ただ、スポット相談を受けていない税理士もいます。



当事務所は、スポット相談を業界で初めて提供しましたヨ
確定申告だけのスポット依頼
税理士に依頼することで、安定した税務処理が確保できます。
確定申告書だけ依頼する、というスタイルもありますが、
月額記帳とセットになっていることも多いです。
税務調査や申告期限に対する不安を軽減できるため、安心して事業に専念できます。
これにより、経営に集中できる環境が整います。
個人事業主は税理士をいらないと感じる理由
個人事業主が税理士をいらないと感じる理由は、
主にコスト削減や自由度の高い経営が可能になる点です。
しかし、事業の状況によっては、税理士のサポートが必要な場合もあります。
自分の事業に合った選択をすることが重要です。
成功事例:税理士なしでの運営
税理士なしで成功している個人事業主の事例も多くあります。
彼らは、税務知識を身につけ、会計ソフトを活用することで、自力での運営を実現しています。
規模は関係ない
ご相談を受けていて規模は関係ないです。
もちろん、副業のような状態では収入も少ないので、
取引が多くないとも言えます。
ただ、これから大きくなっていくにあたり
聞いておきたい、というスポット相談も多く受けます。
自分に合った業務スタイルの見つけ方
税理士を依頼するかどうかは、
自分に合った業務スタイルを見つけることが重要です。
自分のスキルや事業の状況を考慮し、
最適な選択をすることで、より効率的な経営が実現できます。
個人事業主が税理士を選ぶときのポイント
あなたと、あなたの事業にあった
良いパートナーとして税理士を選ぶ方法として
税理士事務所のタイプを4つに区分けしました。
1、総合病院のような規模の大きな税理士事務所
様々な専門家がそろっているので、大企業に向いている事務所。
スタッフが担当するので、
頻繁に変わったり、相性を選べないデメリットも。
2、とにかく低価格な税理士事務所
処理だけに特化した事務所のため、ニーズが合えば良いかも。
3、近所にある診療所的な税理士事務所
良い先生が居ても待ち時間が長いなど、満足度は分かれるところです。
税理士が対応することが多いのですが、処理はスタッフが行うなど業務の守備範囲が多様です。
扱う件数も多いので、常に忙しく対応が遅くなる傾向があります。
4、カスタムメイド型の税理士事務所
熟練の医師1人が、軽い症状から日常の疑問など、親身になって対応してくれるような事務所。
サービスを提供する件数に制限があるため、紹介やタイミングが重要。



当事務所はカスタムメイド型です。私が税理士事務所勤務の時、社長の悩みはスタッフの身では共有できない、社長の相談に早く答えたいと思い、開業18年を過ぎても一人で対応しております。起業家の皆さんの力になりたいと思いました。
税理士への希望例
依頼にあたり、どのような希望がありますか?
これらの他、担当が変わるか、訪問や質問の回数、返答の時間など
コミュニケーションがスムーズに進むことが重要です。
税理士の探し方例
最初の入り口として紹介が多い業界です。
しかしAさんが良いと思っても、Bさんも良いと感じるかは別問題です。
私自身、専門家を紹介する時はとても慎重になります。
探し方の例として、
など


最後に
今回は、個人事業主に税理士はいらないと言われる理由から、
ひとりでできるような方法を合わせて書きました。
個人事業主に税理士はいらないというのは、
しかしながら、税理士へ依頼するメリットも
一度あなたにとって、どのようなスタイルが良いか検討してみましょう。